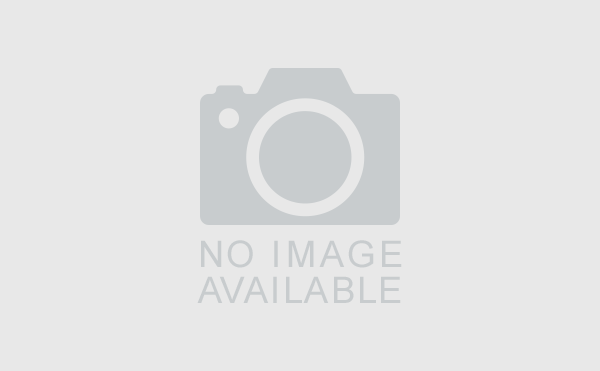小室直樹
存在問題の解決は、人間の“やる気”を恐ろしいほどに増進させる
(=「ある」と信じているものを解決するのは、やる気が出る)
要はリバース・エンジニアリングすることで
商品開発したわけで、
「ある」と信じるものに論理的に取り組むのって、
建設的な行為なんでしょうね。
この点、さまざまな成功例を間近に見ることができる
シリコンバレー、シアトルと比べ、
Uberを締め出して若手起業家の発想を奪うわが国は、
遅れをとって当然なんだと思います。
Googleを始めとするシリコンバレー系企業が
「とりあえずやってみる」姿勢なのは、
「禁止されていなければ何をしてもいいユダヤ教」の精神が
どこかにあるのかもしれませんね。
(日本はやる前から、「やめておいた方がいい」と考える)
ある問題が起きたとすれば、
その問題の対象になっているものが
本当に存在するのかどうかを、まず確認しなくてはいけない
結局、解けないけれども解があるかどうかはわかる、
というのが現代数学の素晴らしさ、恐ろしさなわけで、
もっといえば、現代数学の存在問題の考え方が
あったからこそ、
人間が月へ行くことができたともいえるのである
存在問題の解決は、人間の“やる気”を恐ろしいほどに増進させる。
だからこそ、人に何かを教えたり、仕事をさせたりする場合に、
「まずやってみせることが重要だ」とされるのである
社会学における存在問題の例をもう少し挙げてみよう。
それは、平重盛が「忠ならんと欲すれば孝ならず、
孝ならんと欲すれば忠ならず、
重盛の進退ここに谷(きわ)まれり」と言って
嘆息したという有名な話である。
つまり、重盛は親である平清盛と
主である後白河法皇との対立の板挟みに悩んだ。
そして親への孝行と国家の主への忠誠を両立する道が
閉ざされた状況へと追いやられたわけだ。
それにもかかわらず、忠臣であると同時に
孝子でありたいと望んだ重盛は、
ついにどうにもしようがなくなり、
ノイローゼになって若くして死んでしまったのである
中国の場合には食物規定がまったくない。
極端な話、人間だって食べていい。
それが証拠に、古代中国から清朝に至るまでの
王朝の正史の中にも、人間の料理法の記述が
きちんと載せられている
ユダヤ教では食物規定が、ビシッと決められており、
逆に中国では食物規定が一切ないわけだが、
ともにきわめて論理的な社会といえる
日本の食物規定というのは
状況により、環境によりコロコロ変わる
禁止されていなければ何をしてもいいユダヤ教
いろいろなことを取り決めた最後に“以上、
取り決めたことについて異議が生じた場合には、
双方が誠意を以て交渉に入ることを誓約する”と
必ず書いてある。
だが、これでは、なんとも「契約」とは言い得ない
日本人がひじょうに嫌われるのは、
日本人が規範を持たない民族で、
彼らにしてみれば、「何をやるかわからない」という
薄気味悪さがあるためなのである
欧米デモクラシーの考え方においては、
「これは私の意見です」と言った場合、
当然、「科学とは仮説である」という立場を踏まえており、
「私の意見は一つの仮説にすぎません」
という意味を持っている。
そしてまた、当然、「あなたの意見も仮説にすぎません」と
いうことになる
エンシンオイル、メーカー、OEM仲間の経営塾より