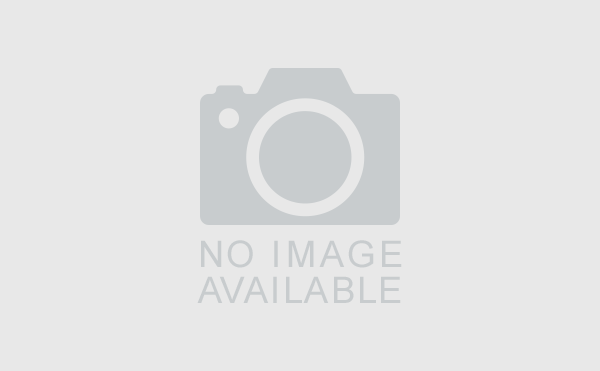日経産業新聞「行動経済学を学ぼう」より
行動経済学の世界で注目されている事象に「埋没効果」がある。これは埋没、すなわち沈み込んでしまって浮き上がれない状況と、それによって起きる不合理な考え方を指す。
企業に置き換えると、企業は何をおいてもプラスの収益が求められる。前年がマイナスだと、なおのことプラスが求められる。この考え方は営利企業活動の根幹で、私たちはこの考え方に依拠して仕事をしている。
ただ、ここに埋没効果が発生する危険性がある。マイナスになった原因を分析する時に、企業活動の対象、すなわちサービスや販売対象を新たな領域に変更するということを考えなくなると埋没効果が出てしまう。企業活動でうまくいかないのであれば、新たな領域にいけばいい。
企業の利益が上がらなくなる理由は2つだけ。努力が足りないのか、方法が間違っているのか。
第4次産業革命とよばれる人工知能(AI)隆盛の状況下では多くの場合努力不足ではなく、現状の方法の陳腐化が理由の場合が多い。過去を断ち切り新たな領域に舵を切ることが求められる。
米国大学のアメフトチームが惨敗してそのチームを廃部にしたというエピソードから。その大学がアメフトの能力を今以上に伸ばせる可能性は低い。そうすると下級生は先輩の借りを返すことに集中してしまう。新しいことに取組むことができるはずの下級生が過去の事象にとらわれてしまうことは避けなければならない。だから廃部にした。
ここで重要なことは、視野が狭くなりどうしても駄目なところから抜け出せない、過去の栄光に捉われ、それに固執してしまうことで判断が遅れてしまう。人間、なかなかコンフォートゾーンから抜け出せません。前例を踏襲しながら、新しいことに挑戦していく。そんなことがこれから特に求められます。
エンシンオイル、メーカー、OEM仲間の経営塾